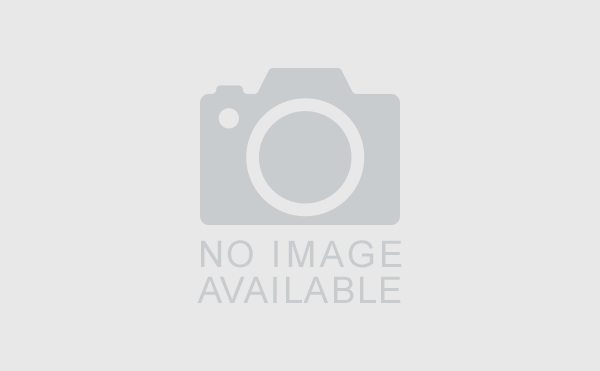旧669回 現代日本版高床式住居
さて今回は、災害対策の形の住居の強化について考えていた所、ふと思い出した昔の住居の形の中に高床式という形で地面から離して高い所に住居を作って住んでいた形があるという事を。
ちなみに今現在でも現代版の高床式住居に相当する住宅等もあるようですがね。
ただ日本では地震頻発地帯という事もありますから通常の高床式住居の形は難しいけども、参考に出来る事は確かであり、必ずしも地上1階に出入口を作らなくても良い事は確かですよね。
今回の話は、今現在も西日本を中心として大雨災害の影響を大きく受けている状況に対して一種の災害対策に向けた住居構造の話です。
大雨で起きる災害の最たる例としては、大雨浸水冠水等の水面上昇による水没や土砂崩れなどの形が起こります。それらに対して現在の住居の基本は地上に付ける物ばかりであり、災害の影響を直撃するばかりであります。
しかし高床式ならば出入口が基本高くなるので災害被害の影響を受ける確率は格段に低くなりますし、いざという時の防犯面等の対策効果も向上出来て良い感じですが、日本特有の状況として地震があるので、通常の高床式住居の形では地震に対して脆い欠点があります。
ついでに強力な水流の流れや土砂崩れなどにも対応する事は難しいでしょう。
ならば高床式の基本的考えは有する形で現代版の形を新たに作り出せばよいという事です。
基本的には2階以上に出入口がある形で、住居の基本部分も2階以上にある事を基本として1階部分は柱だけという脆そうな形ではなく、きちんと住居形式だけども簡易シェルターのような形で本来地下に作り上げる部分を1階に持ってくる形で基本窓は無く進入できそうな部分がほぼ何もない形をベースとしたシェルター形式の1階を作り上げて、その上に本住居を設置する形なら2階建て型高床式住居の形に出来ます。
これなら耐震設計は付けやすく、基本的住居ペースで作りもある程度しっかりと出来るので勢いの強い水の流れや土砂崩れの直撃にもある程度の硬さで対抗させる事が可能です。
1階は基本防御重視の構造で、2階部分以降に基本住居部分を作り上げる形の2階建て建築で、1階部分は基本シェルター形式に部屋等を割り振って使える形にします。
ただし、基本的に浸水等に弱くなる窓の設置は無しだけども、どうしても付けたい場合は完全ロックが可能な頑丈な蓋付きで窓を付ける事も可能という形にします。
そして追加でさらなるシェルター空間増強という形で地下部分に付ける事も建築形式では考えても良いでしょうね。
この形式で1階にシェルター型の住居形式を作って2階以降に基本的住居の形を作れば、現代日本版の災害に強い高床式住居の形に出来て、耐震能力に水害土砂崩れなどに強く津波にも耐えながら防犯能力も向上した形の強い住居形式が作られるでしょうね。
これなら多少低地の立地でも問題なく海に近くてもある程度平気な住居形式で住んで行く事が出来るようになるでしょう。
もしそれでも心配ならシェルター部分を2階や3階にも作る形式で高く上げて行けばよいだけですからね。
ただし、この高床式住居建築方式で1番の問題になってくるのが、出入り口の位置も同時にどんどん上がっていく事になるので、移動が大変になるという点ですね。
階段付けると上り下りが大変になるしスペースも必要であり、移動の不便さを解消する為として従来のエレベーター等を付けると、大掛かり&水に弱い機械のエレベーターでは非常時の備えが心配であり、そこに余計な電気代も掛かってしまうようになり安全性の反面に利便性と電気代がかかってしまうようになる。
なので、エレベーターはエレベーターの構造でも私が前に紹介した水流式エレベーターの形で、水圧によって押し上げる形を地上から2階以降に向けるだけの個人用の形で作り上げるのなら、コスト面も抑えやすく利便性もあまり損なわずに使える形となり、今回の高床式とも合わせやすい形で、水流式昇降エレベーターならば水害時でも使える形になるので、災害に強い特性のまま使える形になります。
それではここまで見て頂きまして誠にありがとうございます。
現代日本版高床式住居~終了~災害対策の家
それにこの住居形式と私が考える道路の階層化は、組み合わせるとより良い形を作り出す形にもなるので、災害供給過多な日本では地上ベースに語るのではなく、全てを高床方式で考えていく形に変えると基本的災害に強く避難ばかりを重視しなくても良い形になって行くでしょうね。
それと同時に移動の利便性向上と犯罪防止効果も併せて高くしていきやすくもなりますね。 END