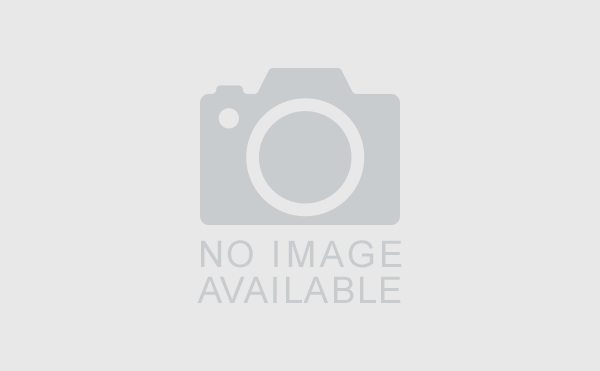90回 米所で水不足 すぐそばにおっきい水溜まり無いです?海
さて今回は、米所に雨が降らなくて、稲作ピンチとなっている報道をよく見るのですが、場所が新潟などであれば、海あり県のはずなのに、いつまで天運任せのダムへの雨貯水で、やろうというバカ中心稲作なのです? 雨の元は何かすら小学校でも習わなかったというのでしょうかね? 教育機関類を一切受けていないというのでしたら、こちらが謝りますが。
雨の大元は、海水が太陽の熱などで、温められて作られる水蒸気の塊です。水蒸気の塊が、熱で上げられて、空気中の冷たい場所で雲となり、さらに冷やされて、雨となって降り注いでくるわけですが、これすら知らないというわけですかね?農家の人たちは。
つまり、何が言いたいのかは理解できますかね?すぐそばに大きな海があるというのなら、海水熱して、大量の水蒸気を発生させて、冷やして固めて、水に変えて、貯水を行なう方式が、人為的に行えるという事であり、天の雨に頼るのは、原始人のやる事です。 昭和を生きてきたというのなら、人工的に水確保するべきですよね?
これに、海水取り込みの時点で、人工滝発電と組み合わせると、大量の電気も作れて、水も作れる形となり、一石二鳥であり、貯水池は町の地下側に作り上げて、大雨災害対策にも繋げつつ水流交通も併設させると、さらに運用効率は上がり、全部活用して、災害に強く、水不足も無く、電気代削減にも繋がる仕組みに変わるわけですが、全部天運任せで努力一切せずに、自殺したいというバカが今の農家ですか? それも消費者巻き込んで、拡大自殺。
海水を人工的に熱して、水蒸気に変えて、その水蒸気を集めて水にする仕組みは、ごく一般の自然科学の話であり、ろ過とか浄水よりも楽で、近くに海があれば実行できる大量の水確保術なのですが、これを無視して水不足というのは、片腹痛い気がしますけどね? 海無し県が水不足言うのであれば、その通りですが。
水の大元どこにある?天から魔法のように生み出されて作られるわけではなく、海が暖められてから作られるという、小学校ロースクールの授業で習う範囲の科学の原理を忘れたとは言わせませんよ? もしくは、カップ麺作る時とか、お湯沸かす際の湯気の存在を知らないとも言わせませんよ?(一般的な町に住む人の中で。
水は、自然の海のある場所から作り出せる物なのですから、人間も自然に習って、同じ事をすれば、水不足で困るというバカはしないはずですが?
それでは、ここまで見て頂きまして誠にありがとうございます ~終了~