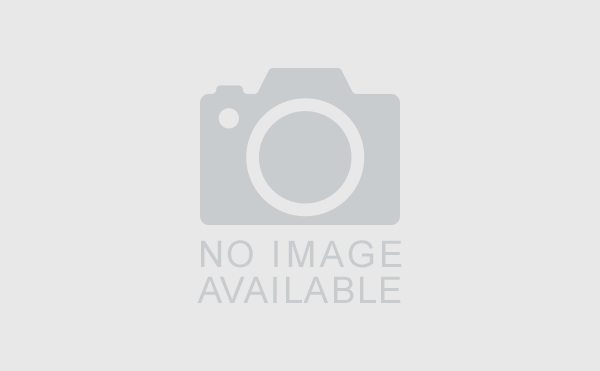41回 報道特集から 日本のお米の今後
さて、興味関心のある報道特集の時に作り出す話として、今回は日本の米不足騒動で、米高騰になっているけども、生産者も消費者も苦しむのに、高くなったお米のお金はどこに消えた?というのは、前に話した所で、諸悪の根源である自民党政府とJA農協の元に隠されていると見た方が正しいでしょうね?
そもそもの国内だけに目を向けて、米が余ったら減反をした方針自体が間違いであり、海外輸出に向けて検討して、更なる米農家の利益拡大に繋げていけば良かった物を、内向き経済で、日本国内主体に考えた事が間違いで、それをつい最近の自民党政権も継続し続けた事が、過ちだったとみるべきですよね?
JA農協が、米高騰の一因になっている可能性が高く、そこ無視して販売流通を考えられる形を新たに作り出していく方が良く、昔言われたヤミ米の方が、本当に消費者を助けるお米だったと言える状況ですよね? そもそも、日本は消費者に届ける為の中間業者が多すぎていて、それが余計に米高騰に繋がっているともされて、海外だと、JA農協と卸売りが合体した物が普通で、別個になるとそれだけ価格が上がりやすいという事で、消費者の負担が大きくなるという事でもあるようですね?
この辺は、下請け孫請けで、無駄税金が増えまくる自民党の現金給付などの政策と似通っている部分で、連帯感が強く印象に残る仕組みですよね? 結局、国民や消費者を食い物にして、お金を巻き上げようとする奴らが作り上げている仕組み。 ただし、それも資本主義から見れば普通の流れ。
現状で、米不足米高騰を抑える為に必要な事は、生産者農家と仲介業者1つくらいに小売店などと繋げる事で、生産者も消費者も助ける流れを新たに作り出す事が必要な仕組みであり、国が役に立たないならば、市町村などが頑張って、新しい農業の形で支援して、農業も令和版の全く新しく、海外に負けない形に変えるべきですよね?
天候や気温の影響に負けない形で、お日様農業から、屋内機械化の全自動型農業工場の形に変えていく方向で、市町村も一緒になって、村や町おこしの復興に繋げて行く流れから、安定して安い食料生産体制を確立させて、生産者の確実な利益と、消費者も確実に助かる形に変えていくのを、やっていく方向性が良いでしょうね。
事は、食糧安全保障にも関わってくる事であり、食料自給率の確保とともに、日本の輸出産業拡大と、世界の貧困対策にも役立てる方向で、バンバン食料生産に繋げて行く方向性が良いでしょうね? 加工技術に保存技術も格段に向上していますから、大量生産しながら長期保存できる形から、全世界に向けて輸出できる形で見据えれば、減反するメリットはどこにもなくなるでしょうね?
ついでに、牧畜関連の飼料なども日本で国産型に繋げて行ける形も取って、海外に頼り過ぎない完全自給自足型の農業や牧畜関連を強化していくべきでしょうね。 その為にも、屋内型の完全機械型農業の形を一般主流化させていくべきです。町の発展や復興にも繋がるのなら、市町村も協力を惜しまない方向で出来ますよね? 食は経済の下支えに繋がる物であり、人が生きる為に大事な要素ですからね?
農業も二次元中心ではなく、三次元やVR化させていくべきです。 この方法でならば、簡単お手軽農業としての参入拡大に、担い手も増やしていく事は可能となります。 そこから、改良や販路拡大にも役立ってもらう流れでね? 基本生産は機械に任せて、改良や発展に販路拡大などは、人が行なっていく作業分担をするべき。
それでは、ここまで見て頂きまして誠にありがとうございます ~終了~