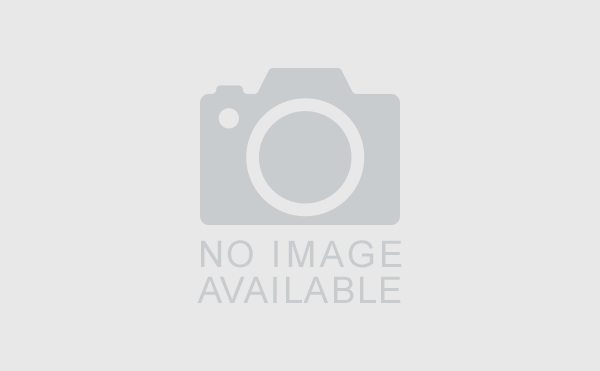100回 災害被害から元通りを目指す?再度受ける被害の繰り返し
さて今回は、なぜ災害は繰り返すのか?という話についてですね。 先に答えを言えば、災害を受ける前への元通りを目指したら、そりゃ同じ災害規模が来たら、また同じように破壊されて、大災害になるという簡単な道理ですが、それすら思いつかない人が多いのでしょうね?
災害に弱い状況があったから、災害たりえる形になって犠牲も出ているというのに、それを理解せずに、災害を受ける前への元通りを希望したら、反省と教訓が何も得られないまま、再度災害を受け入れる体制で、災害となって被害は繰り返し起こり、何度も被災するという事になります。
つまり、災害復旧などの先にある事が、昔に対する元通りでは、同じ以上の災害が必ず訪れる状況になるだけであり、バカの繰り返しにしかならないという事です。 大災害では、必ず過去の教訓を生かして、同じ災害を引き起こさせない為の策を講じる必要があるわけですが、そこに元通りは、それをする気はないという意思の表れでしかない。
故に災害から立ち直る為の言葉での復旧や復興には、昔への元通りではなく、昔以上の形に進化させていく必要があるわけです。 災害に対して対策を打って行く為には、問題や課題に対して解決策を探っていき、日々進化させながら、災害に遭わない町作りをしていくべきであり、そこに必要なのは、昔には戻らない進化していく形だけです。
昔のままにどうにかといった所で、災害は待ってはくれませんし、同じ災害を何度も受けていては、心が折れる人や財力に余裕がなくなる人が増えて、その場所から去ってしまう事も増えていくでしょう。 故に元通りを目指す形は未来が無いわけで、同じ災害は災害にしない為の努力と進化を重ねなければ、未来ある安心の町作りと復興には繋がらないという事です。
それで、世界でもですが、日本で大きな災害になっている現象は、大雨災害からの町冠水や水没状況に、土砂災害・土石流の発生や河川氾濫など、大雨災害関連中心です。 原因は地球温暖化現象の形と言われていますが、単純に地球が熱くなっているからという所で、温められた海水からの水蒸気大量発生で、大雨災害レベルの雨雲や雷雲が大量発生しているからであります。
これを一朝一夕でどうにかする事は不可能ですし、説得や話し合いなども効かない、自然からの一方的な物量攻め戦争攻撃であり、災害対策という国防は必須の対応であるのですが、その為の予算も作る必要はあり、日本全体の災害対策の必要性の心構えも必要です。
災害被害を受けたら、昔への元通りを目指すのではなく、より災害に強く安心できる町作りへと変えていき、自然災害多発な状況でも、災害に負けない町へと作り変える事で、安心を提供して、より豊かな町へと変えていく努力が必要という事です。
この努力を怠れば、災害は再度災害として繰り返され、何度も災害被害で被害が重なっていけば、人は離れて、町が滅んでいくだけとなるでしょうね? つまり、昔への元通りを願えば願うほど、町は滅んでいき、元通りに遠のいていく現象が起こるという事です。
本当に大事なのは、昔への元通りではなく、町を維持存続させて、人々が災害に負けず安心して過ごせる場所を守る事であり、その為には、災害に負けない町作りの為に、災害対策を日々強化していきながら、進化し続ける町作りに変えていくべきという事です。
昔には戻らず、町を守り、人の暮らしを守る為に、周辺環境の変化とともに、適応していく為の進化を常に更新していく必要があるという事ですね。 災害を受けたのだからこそ、早急な無計画の復旧ではなく、きちんと再被害を受けない為の対策込みの進化をしていかなければ、未来無き消耗戦を強いられるだけになって、困窮していく人は増えていくでしょうね?
大雨災害レベルの豪雨が日常になってきている今としては、昔のような車や電車という交通は使えない物になってきており、大幅なアップデートの必要性に迫られているわけです。 それも、困窮する庶民の手の届く範囲でね? 故に高くなる水陸両用車への一般販売は無駄な対策でしかない。
大雨豪雨に強い交通と言えば、雨でも問題なくできる手段は、水路を使った交通もしくは、道路全てを建物で覆う事でしょうね? ただし、道路を全て建物化するには、途方もない時間がかかり、すぐさまの対策には、程遠いでしょうから、水路を使った交通手段を増やしていく方向で、水流交通の形に変えた方が良いでしょうね?
同じ水路式でも、船の動力で動かす形では、大雨災害レベルに対応しきれず、船が転覆したり、衝突の危険性が高まるだけですから、安全性も同時に担保させたいならば、自動交通化にも繋げ易い、水流交通という水の流れを主体にした、交通スタイルに変えるべきでしょうね?
乗り物が自由に動く状況は、同時に大きな危険と別種の災害も生み出していく物ですから、船形式の自動化を目指すのが、大雨に強く安全な交通手段となっていくわけです。 これなら、低地水没で交通寸断の可能性は無くなり、大雨や大雪からの災害交通ストップは確実に無くなるでしょうね?
ただの水路に船動力式だと、冬の大寒波襲来時には、交通が完全ストップする危険性がありますからね? これが水流交通ならば、流水は凍りませんからね?ついでに、流水からの水力発電で、同時に電熱化させれば、より凍りにくい形が実現可能にね?
道路部分への建物化の立体階層道路などは、山間の部分を中心に作り上げていくべきであり、土砂災害の食い止め壁の形として、さらにクマが山から下りて来ても、町に侵入できない為の壁としても、機能させていくのが望ましいでしょうね? 移動も可能な道路の形から、壁の機能にも変化させていく。
もちろん、一般道は水流交通とすれば、土砂災害の多量な水分を抜く形に、土砂木材の適切な自動搬送にも活用でき、クマも壁を突破したと思ったら、次はお堀で流れが速く、強行突破は難しいとすれば、断念するでしょうし、穴を掘った所で、侵入不可の状況に、強引突破怪力でも、その後溺れるだけでは、絶対に侵入できなくなるでしょうね? そして得られる町の安全。
さらに、町の地上部分が被害を受けやすいならば、地上1階部分はシェルター形式や何もない空間で、予めの事前対策として、被害を防ぐ方向性を作り出していくべきでしょうね? 安全性を重視するならば、1階部分は、強固なシェルター化を建築の義務基準にまで押し上げて、現代型高床式建築にしていくべきでしょうね? 昔の人が見たら、大きな岩の上に家を建てるのか?という具合に。
念には念を、対策は1つではなく、複数を常に選択していき、あらゆる状況の災害に対応していき、どれかが仮に突破されても、他で食い止め、被害を最小限にしていく形こそが、安心できる町の形になり、安心できて命が守られる町ならば、確実に他の町よりも人が集まりやすい形になっていくでしょうね? 安心安全な場所は、全ての土台ですから。 危険な場所に居たい奴は極少数。
それでは、ここまで見て頂きまして誠にありがとうございます ~終了~