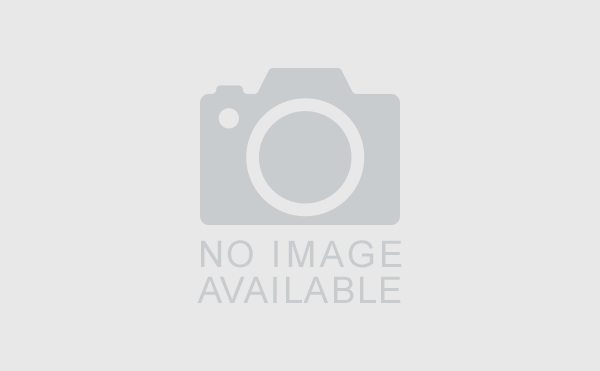旧92回 防災建築Ⅺ 対津波対策の家 耐えるのではない!流れに乗るのだ!
以前流される家というのを紹介しましたが、今回はほぼ津波専用の対策でお届けいたします。衝撃吸収とボート系はあまり変わらないので、類似点がいくつかあると思いますが、今回は前よりも建築しやすい対策方法になっております。
以前は浸水メインで津波に関してはごつい感じの難しい建築になっていましたが、今回のコンセプトは津波による第一波を受けた後は、そのまま流れに乗って行ってしまおうという感じです。要は耐えない。共に流されることにより人的被害や家の被害を最小限にしようとするのがメインの考え方です。島国の日本ですからこういう対策を考える事も1つの手です。 未然に防ごうとしたら時間もお金も莫大かかり、次が来るまでに間に合わない可能性も出てくるでしょう。
しかしこの対策なら個人単位で行えるし、避難所での個人の憩いが取れなくストレスや病気の蔓延にかかる事を減らすことが出来、新たな住まいを探すという事をしなくてよくなります。
だってもし家が無事だとしても周りが住むことが出来ない環境になっていれば、どのみち移動できない家では手放しも考えないといけなくなりますからね。(それに無傷の可能性は低いし)
流れに乗ることが出来るという事は、つまり水の力等があれば家を動かすことが出来るという事になります。土地はどうにかしないといけないでしょうが、家だけでも無事であれば防災の面から見ても良い状況に繋げられる確率が高くなるのではないでしょうか?
流れに乗るという事は、家の下に緊急時にボートを展開できるようにする必要があります。多少の障害物等に耐えられるように頑丈な繊維でボートの部分を作る必要があります。このボート部分は普段は家の下に隠れて配置(空気を入れて無ければ簡単ですよね?)しておき、緊急時の時に自動や手動でライフラインを強制的にいったん解除(多少の自家発電機能の保有必要)してボートを展開できるような状態にする。このボートは家の下半分位を覆えるような大きさにする事。 また解除したライフラインをまた同じ場所で繋ぐ場合は、手動で行えるような配置にしておく。
次に津波対策の部分ですが、緊急時に家に設置しておいた機械等で水に触れると膨張したり固くなる物質を家の周囲に展開させて、津波による家の倒壊を防ぐ。屋根などにこの機械を取り付けて、ボート作成と同時にこの機能も作動するようにしておく。
要は一瞬でもいいから津波の一撃を受け止められるようにすれば良いという感じだ。(あとは流れに乗って奥まで運ばれるから第二波や三波をあまり気にしなくてもよくなる。)
ちなみにこれは浸水対策としても使える。しかし固定は今回考えていないので、多少ずれる可能性がある。
それでは今回は本当に終わりにさせていただきます。
防災~終了~津波