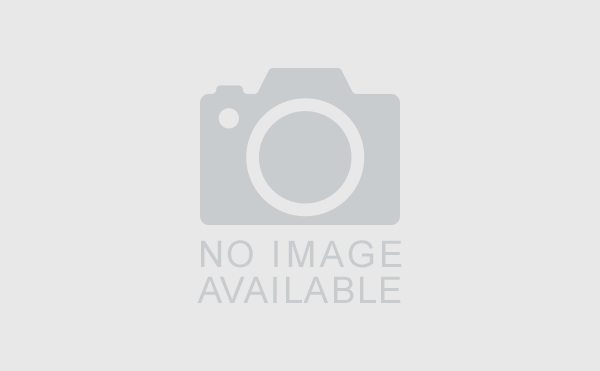旧473回 報道特集特集 ゲノム編集食品に対する意見
今回の話は、報道特集の特集内容ですね。今日放送されたのはゲノム編集食品に対する話で、別にゲノムしなくても可能な方法の話をします。
ゲノム編集食品というのは、人間側の怠惰から生み出した早期的な科学技術ですね。
今回の食品に対する話の見解ですけども、それと似たような事を自然に発生させて変えていく方法もあるのに、それが面倒だといきなり直接遺伝子いじって変えてしまえばよいという短絡的怠惰な考えから生み出された技術であるという事ですね。
今回の例として挙げられたサバの共食いやマグロの神経質に関する対処法はゲノムに頼らずとも存在します。
ただ方法が少々面倒だから、楽が出来そうな所に必死に力注いだというわけですね。結局苦労はそれほど変わらないというのに、バカな専門家や教授たちですよね。(笑)
それで安心性が疑われる状況では、なんのこっちゃという現状況という感じですね。
ニュースでも取り上げられている豚コレラの拡大に関しては、養豚場の安全体制を今の倍以上に引き上げれば完全に防げるのに、ゲノムに頼ろうとするとか、本当にバカな人たちばかりで、基礎研究など舐めてますよねあのバカ共って感じです。
普通に豚コレラ対策として養豚場の環境を食品安全基準として徹底的な管理状況に関する衛生環境をきっちり守る体制に変える事が出来れば、豚コレラなど恐れるに足らずですよ。
豚の育成施設の環境を最低基準にしているから、そりゃ豚コレラに掛かりたい放題は確定的だというのにね。
それでサバの共食い防止策というのは、単純に現状狭い場所で大量に育てようとしているから発生しているわけですよね? ならば遺伝子的にも学習させる目的で、共食いをする必要が無い事をサバに覚え込ませれば、無理にゲノム編集に頼る必要性はないという事になりますね?
方法としては温室育ちを少数育てて、共食いに至る必要性を数世代に渡って全く必要無いという状況にまで覚え込ませれば、その可能性を限りなく低くまで抑え込む事は可能でしょうし、また他の集団行動が基本の魚の行動例を応用させて、あえて幼生のサバたちに脅威となる天敵を放り込んで引っ掻き回させる形をこれまた数世代にわたって繰り返せば、必然的に種の生存本能として生き残る為には集団行動の必要性の意義を覚えて、共食いを減らさせて集団行動で身を守る形に進化させて防ぐ方法もあるのではないでしょうか?
また、この勉強学習の体系以外にもAIによる統括管理で棲み分けをしっかりさせる形で、大きさによって過ごせる環境を随時変えさせていく方法によって、共食いの発生に至る可能性を限りなく減らして行く流れにする事も可能なはずです。
AIが無くても大きさの違う網の壁等によって、必然的に小さいサバが小さい網をくぐって安全な場所に逃れられる状況の生育環境を作れれば、共食いから逃れて生き残れる形にさせやすく出来ます。
あとは短絡的な方法で、1匹ずつ分けて多く育てられる環境を作り出す辺りですかね。そして成長したら大きさによって分けてまとめるとかね。
次にマグロの神経質に関する内容としては、こちらもサバと同じように少数精鋭で温室暮らしでのんびり育成する事を数世代に渡って覚え込ませて、神経性を鈍くさせて学習させる事は出来るでしょう。
もしくは刺激を与えさせても暴れさせる事が出来ない状態にさせて、その行動抑制による内容で刺激に対して慣れさせて神経質な形を無くさせる学習方法もあるでしょう。
またこちらも学習体系以外の方法としては、こちらもAIによる人間以外の刺激を与える事無く育成できる環境にて、外部刺激を限りなく無くさせて育成する事は可能で、その他にも壁にぶつかって突撃死を無くしたいのなら、そもそもそんな壁を無くしてマグロを傷つけない柔らかな網や繊維などで優しく力を分散させて、優しく方向転換させるような物質で周りを囲むような形に変えれば、突撃死は限りなく無くせると思いますがね。
あとは人間が手を施せる部分を限定的にさせて、可能な限り刺激を与えさせない暗室空間育ちの環境にする事も可能ですね。
このようにゲノム編集に頼らずとも、いくらでも対処する可能性は残されているのですよ。
それをバカな科学者共が短絡的に解決できないか悩んだりして、産みだした技術がゲノム編集技術(食品版)というわけですね。
だから私が食品に関するその技術を軽くバカにするのも分かる話でしょ? 植物に関しても私の屋内農場を使えば、いくらでも大量増産態勢は整えられますし、短絡的なバカ研究者共がゲノムに頼ろうとするという事ですね。
それらをすべてやってきてダメだったというのであれば仕方ないですが、その可能性すらも見いだせずにやろうとしたら、単純バカでしかないという見解ですね。
それではここまで見て頂きまして誠にありがとうございます。
報道特集~終了~ゲノム編集